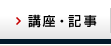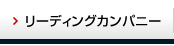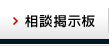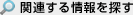奨学金返還支援で優秀な人材を確保!
現在、大学生の約3人に1人が奨学金を利用していることはご存知でしょうか?貸与型の奨学金を利用した学生は、卒業後に返還の義務を負いますが、その経済的負担が若者のライフプランやキャリア選択に影響を与えています。こうした状況の中で、自治体が奨学金返還の支援制度を設ける動きが加速しています。本記事では、奨学金制度の現状と、自治体が支援に取り組む狙いやその効果を具体的な事例とともに紹介し、民間企業が実施できる施策についても紹介します。
【奨学金制度の現状】
日本学生支援機構(以下、JASSO)によると、令和5年度には、大学生の約3人に1人が奨学金を利用しています 。企業の新卒社員の約3割が奨学金の返済を抱えている計算になり、既存社員を含めると従業員の約10~20%が返済中であると推測されます。
奨学金の平均貸与総額は一人当たり約313万円で、卒業後15年ほどかけて返済するのが一般的です。注目すべきは、少子高齢化が進む中で、JASSOの総貸付残高は過去10年間で約2兆円も増えているということです。これは、過去30年間で平均年収がほぼ横ばいである一方で、物価や学費は上昇し続けていることが影響しています。奨学金制度はこの差を埋める形で、学費負担を補う役割を果たしていますが、その返済負担が若者のライフプランにも大きく影響を及ぼしています。
「貯蓄ができず転職や独立に踏み切れない」「結婚や出産をためらう」といった声も多く、奨学金の返済が個人のキャリア選択やライフステージの決定に及ぼす影響は、企業にとっても無視できない課題となっています。
【自治体で広がる奨学金の返還支援】
このような状況を受け、自治体を中心に奨学金返還支援が拡大しています。日経新聞によると、2024年度には全国の市区町村の約半数にあたる816の自治体が奨学金返還支援制度を導入しており、過去5年で倍増しました。制度導入の狙いや具体的な支援内容、その効果について、事例とともにご紹介します。
事例1. 山形県
山形県は、県内全市町村と連携して奨学金返還支援を推進しており、制度を導入している市区町村の割合は100%と、全国で1位です。2023年度までに、212人に対して総額1億1000万円以上の補助金を交付しました。吉村知事は「単独での支援よりも規模を拡大し、多くの若者に充実した支援を提供することで、県外流出を抑制し、県内への定着を促したい」と述べています。
事例2. 愛媛県
愛媛県では、県内企業が中心となって登録する奨学金返還支援制度を導入し、企業と県が基金を積み立て、奨学金の返還に充てる仕組みを整えています。合成樹脂製品メーカーの福助工業では、この制度を活用して14人の社員を採用しました。現在、142社が登録し、92人の利用者がいるとのことです。県の狙いは、「地元産業を支える人材の定着やUターン促進」にあります。
事例3. 栃木県
栃木県は「とちぎ未来人材応援事業」として、県内企業の寄付を活用した基金から、卒業2年前の奨学金借入分に対し最大150万円を助成する制度を実施しています。県内就職を条件としており、2024年度には定員50名に対し128名の応募がありました。県によると、結婚や定住を見据えた長期的な支援策としての意義を強調しています。
|
|
株式会社アクティブアンドカンパニー 代表取締役社長 |
|---|---|
|
私たちは成果創出に寄与する活性化施策を提供することを通して、躍動感溢れる未来を創造していきます。 株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役社長 株式会社日本アウトソーシングセンター 代表取締役社長 |
|
専門家コラムナンバー
- 採用ブランディングを高める!印象に残る会社紹介動画の作り方 (2025-09-29)
- 新人が潰れる職場の特徴5選とは?いくつ当てはまる? (2025-09-11)
- 4コマ漫画「オンボーディング」/聞いていいのに聞けない空気 (2025-07-03)
- 4コマ漫画で「採用」あるある/あなただから一緒に働きたいんだ (2025-06-02)
- 選ばれるインターンシップとは?(後編) (2025-05-29)